最近、あるオンラインサロンで話題になっていたのが「高速道路での逆走」に関するニュースです。皆さんもテレビやネットで目にしたことがあるかもしれません。
実は、全国の高速道路では2日に1回のペースで逆走が発生しているそうです。中でも、約37%が分合流部や出入口付近で発生しているというデータが出ています。 さらに注目すべきは、逆走したドライバーの68%が65歳以上、そのうち46%は75歳以上という数字。高齢ドライバーによる逆走が、深刻な社会課題になっていることがよく分かります。
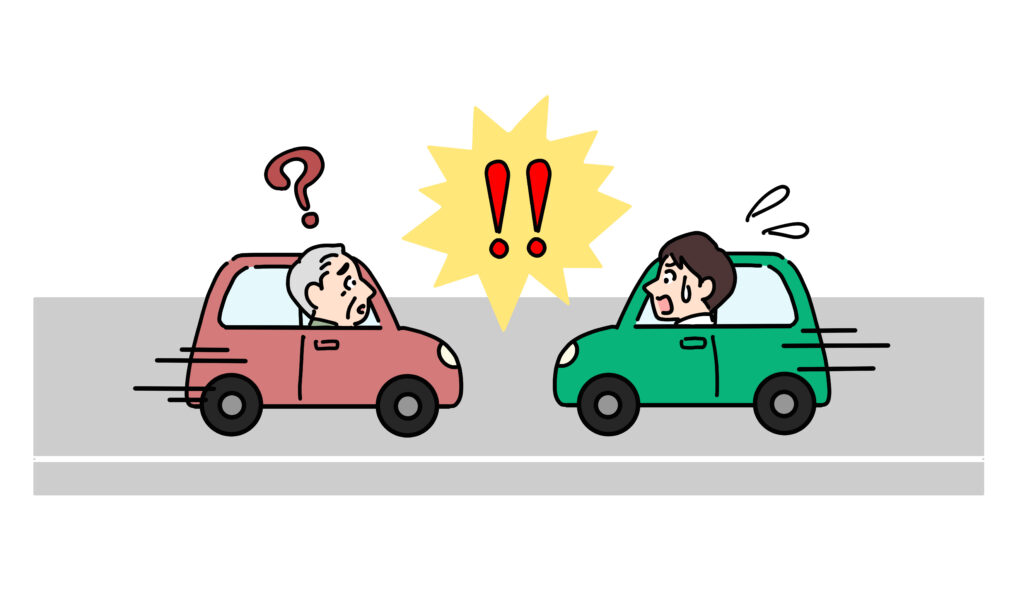
とはいえ、「運転せざるを得ない現実」もある
一方で、高齢ドライバーの方が運転をやめられない理由も、現実として存在します。
例えば、地方に住んでいる方にとって、自家用車は生活の必需品です。近くに公共交通機関がない、もしくは路線バスが廃止されてしまった…そんな地域も増えているのが現状です。 買い物、通院、地域の活動――それらを支えているのが“自分の車”という方も多く、簡単に「運転をやめましょう」とは言えません。

「逆走」対策とともに、地域交通の支援も急務
高齢ドライバーによる逆走を防ぐには、道路側での対策(標識の強化、誤進入防止の構造など)はもちろん、ドライバー本人へのサポートも必要です。
それと同時に、地域全体で高齢者の移動を支える交通インフラの見直しも欠かせません。
・地域内移動をサポートする乗合タクシーやコミュニティバス
・買い物代行や移動販売といった新たなサービスの導入
・若者や地域住民による“運転のサポート”体制づくり こうした取り組みも、今後ますます重要になっていくでしょう。

高齢ドライバーの逆走問題は、単に「運転技術の問題」ではなく、「暮らしをどう支えるか」という、より根深い課題とつながっています。 御社としても、地域の安全と生活を守る一員として、こうした課題に関心を持ち続けたいと思っております。
